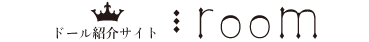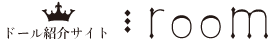姉からの頼みごと
「姉さんがおつかい…僕たちに?」
珍しい、と僕は思った。目はあまりよくないけれど、ものともしないで自分でなんでもこなしてしまう姉からの依頼だった。
となりのソファーに腰を下ろしている弟も、静かだけれど耳をピンと立てて話を聞いている。
「そ、頼まれてくれない?お礼は勿論するわよ」
「お礼なんていいよ。それで、おつかいって何を買ってくるの?」
「花よ」
「「花……」」
思わず弟とシンクロしてしまった。姉さんが花を買ってきてくれだなんて…逆に貰うことは仕事柄多いみたいだけど、凄く珍しい。
そもそも姉さんは目があまりよくない、特に色を認識する組織がなんとかで色を識別することが難しいって兄さんが教えてくれたんだ。
「…なあに、その顔。どうしたのって書いてあるわよ」
「…珍しいな、と思って。何かあったの?」
弟が僕の代わりに答えてくれた、確かに何か理由があるはずだ。
「実はね…」
姉さんの話では、いつも公演を観に来てくれる女の子がいるそうで、最近見かけないと思っていたらその子が入院していると人づてに聞いたらしい。
幸い命に別状はないけれど、元気がないらしくお見舞いに行きたいんだって。その子がいつもくれる、リィデーリタの花を大きな花束にして。
色は識別できない姉さんだけど、兄さんや他の団員たちから淡いピンクの色をしているらしいということは教えてもらっていたみたい。
「姉さんらしいサプライズだよね!」
「…たしかに」
そんな理由があると聞いたら、おつかいに行かない選択肢はないよね(そもそも断る事はないけれど)。
とりあえず街にある花屋さんを近い順番に当たっていく事にした僕たちだったけれど、中々目当てのリィデーリタの花が見つからない。
あるのは薄いオレンジか黄色の花弁のものばかりで、店員さんに聞いてもピンクのものは珍しいものとのこと。最後に当たったお店の店員さんが、もしかしたらと一件、町外れにある家を紹介してくれた。約束は出来ないけれど、その家の方が育てているという話を以前聞いたのだと。
店員さんが書いてくれた地図と住所を頼りに、僕たち2人はその家に向かう事にした。
「これはまた…」
「立派な…」
貰ったメモと家を交互に数回弟と確認するが、間違いなくこの家のようだ。
門が立派なこの家は、敷地がとても広いようで門から家を確認する事はできなかった。恐る恐るベルを鳴らして暫く待つと大きな門が開き、中から小さなおばあさんが現れた。
「あらまぁ、随分とお若いお客様ねぇ。なにかご用事かしら?」
「初めまして、僕はノイル。こっちは弟のローアです。フェルメーラさん…ですよね?こちらに僕たちの探している花があるかもしれないという話を聞きまして…」
「ええ、私がフェルメーラよ。お花を探していらっしゃるのね、家にあるかしら…」
「リィデーリタの花、です。薄いピンク色をした」
「まあ!リィデーリタの花でしたらありますよ。さあさ、立ち話もなんですわ家に寄っていらっしゃいな」
ここに来た経緯を話しながら門から庭に向かって暫く歩いていると、突然目の前に色とりどりの花畑が現れた。
「……綺麗だね」
「凄いな……」
驚く僕たちに、フェルメーラさんは微笑みながら教えてくれた。花が大好きなフェルメーラさんご夫婦が大切に育てている花畑だということ、旦那さんが2年前に亡くなってからは一人でこの花畑を手入れしているということ、そして僕たちが訪ねてきてくれたことがとても嬉しいということを。
「私たちが大切に育てた花が誰かのお役に立てるなら、主人も私もとても嬉しいわ」
さあ、こちらへと花畑の先に案内されると、そこには目当ての薄いピンクのリィデーリタの花があった。
他にも薄いオレンジや黄色のリィデーリタの花もあり、とても気持ち良さそうに風に揺れている。
「もしかして兄さん、同じこと考えてる…?」
「うん。だってその方が良いって僕も思うからさ」
2人で顔を見合わせて、フェルメーラさんにお願いする。
「「リィデーリタの花を、3種類分けてください。お願いします」」
一瞬、驚いたようなフェルメーラさんだったが、すぐに表情を綻ばせ手を叩いた。
「まあまあ、なんて素敵なお願いかしら!きっと素敵な花束になるわ」
そのあとは奥に見えていた家に招いてもらい、お茶をいただきながら色んな話を聞いたり話したりしてあっという間に時間が過ぎていった。
花に手慣れたフェルメーラさんが帰り際にリィデーリタの花を綺麗に花束にして僕たちに渡してくれた。
「また、いらっしゃいな。今度はお姉さんも一瞬にね」
「はい、話しておきます」
「今日は本当にありがとうございました!」
家に帰った僕たちは、姉さんに今日あったことを伝えてリィデーリタの花束を手渡した。
「そんな事があったのね…2人ともありがと。それじゃあ今度は私がお礼をする番ね、今度フェルメーラさんの家に連れて行ってくれるかしら、兄貴のとびきりのお菓子を持って行こうじゃない!」
「…良いね」
「だね、フェルメーラさんきっと喜ぶよ」
後日、女の子のお見舞いに行った姉は、眩しいぐらいの笑顔をもらったと話してくれた。
色の識別が難しい姉が眩しいぐらいと言うのだから、それはそれはとても素敵なものだったに違いない。
その笑顔が見れたのは、フェルメーラさんを始め色んな人たちの優しさが繋いだものだということを、僕は知っている。
僕もそんな優しい人でありたいと、改めてそう思った出来事だった。